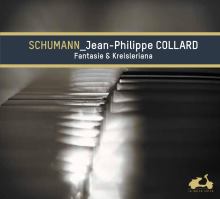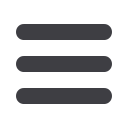

33
ジャン=フィリップ・コラール
《クライスレリアーナ 作品16》
“クライスレリアーナ”というタイトルは、
E.T.A.
ホフマンの同名の音楽評論集(
1814
)にちなん
でいる。この評論集に登場するのは、激昂しやすい性格をもつ楽長、ヨハネス・クライスラー
だ。ホフマンは小説『牡猫ムルの人生観』でも、クライスラーの架空の伝記をつづった。シュ
ーマンがクライスラーに自らを重ね合わせ、音楽と文学が呼応していくさまは、魅惑的であ
る。ホフマンの小説は《クライスレリアーナ》と、実に深い次元で共鳴しているのだ。作曲中
の
1838
年、シューマンはクララとの関係を猛反対され、辛い境遇にあった。クララの父の嫉
妬深い監視を乗り越え、
2
人は周囲の協力を得て時おり落ち合うこともあった。クララはさら
にヴィルトゥオーゾ・ピアニストとして、プラハやウィーンで《謝肉祭》の演奏を成功させてい
る。《クライスレリアーナ》は、フロレスタン(活気あふれる
5
曲)とオイゼビウス(メランコリックな
3
曲)の間で絶えず揺れ動くが、それは天才シューマンのロマン主義的な二面性を物語っ
ている。作品全体を駆け巡るのは、緊迫、優しさ、詩情、イマジネーション、激しい情熱だ。
《謝肉祭》を締めくくる率直な歓喜とは打って変わって、《クライスレリアーナ》の強迫的なリ
ズムが植えつける漠とした不安は、何一つ晴らされることはない。曲尾の数小節は、鍵盤の
深部へと沈んでいく。それは最後のホフマン風の旋回に喩えられるだろう。不気味な地の
精は――ラヴェルが後に書き上げる<スカルボ>(《夜のガスパール》)のように――気を
失うが、消え失せはしないのだ。