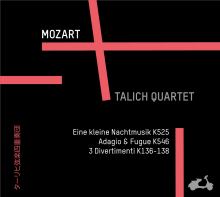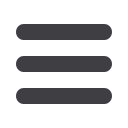

37
ターリヒ弦楽四重奏団
ディヴェルティメント 変ロ長調
K.137
は、非常に変則的なつくりでできてい
る。「アンダンテ」が最初に置かれているのだ。これによって、その後に続く「ア
レグロ・ディ・モルト」とのコントラストをより強調する効果がある。「アンダン
テ」のバランスは完璧で、荘厳さ、リズムの躍動感という特徴に加え、第
1
ヴァイ
オリンがカンタービレで演奏することでドラマ性のあるコントラストが柔げられて
いる。
終曲の「アレグロ・アッサイ」は、ロンド形式である。低音部が活気をもって刻む
頑丈な農民のダンスが、ロンド形式の中に優雅に隠れている。音楽はただ人々を楽
しませようという意図でつくられており、それ以外の底意はない。
ディヴェルティメント ヘ長調
K.138
の色彩が、イタリアとドイツのバロック音楽から
借用されていることは明確で、他の
2
曲よりも明らかに『ザルツブルグ・シンフォ
ニー』の名称を正当なものとしている。
聴いてまず感じるのは、活気にあふれたテーマがイタリアを描き、構成はミカエ
ル・ハイドンの書法に範を取っているということである。もちろん、第
1
ヴァイオ
リンが優位を占めている。
「アレグロ」「アンダンテ」「アレグロ」の
3
つの楽章がこの『デヴェルティメン
ト』を構成しているが、同名の他の曲は最高で
7
楽章を含んでいる。(「ディヴェ
ルティメント」の伝統としてメヌエットが
2
曲あるが、それはここでは省略されて
いる。)
第
1
楽章「アレグロ」では第
1
ヴァイオリンの奏でるメロディーが主導力となってい
る。「アンダンテ」はシンプルかつ深い美しさにあふれている。このようなテーマ
の扱い方を通して、若いモーツァルトがすでにもっていた独特の書法を見分けるこ
とができるのだ。その書法は、生まれたばかりの弦楽四重奏曲と、交響曲の間で揺
れ動いている。終曲の「アレグロ」は、オペラ・ブッファのような一種のロンドで
ある。ここにはいやでもイタリアの「シンフォニア」の魅力が聞き取れる。