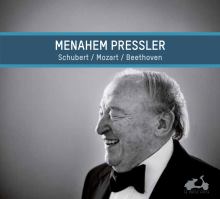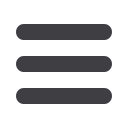
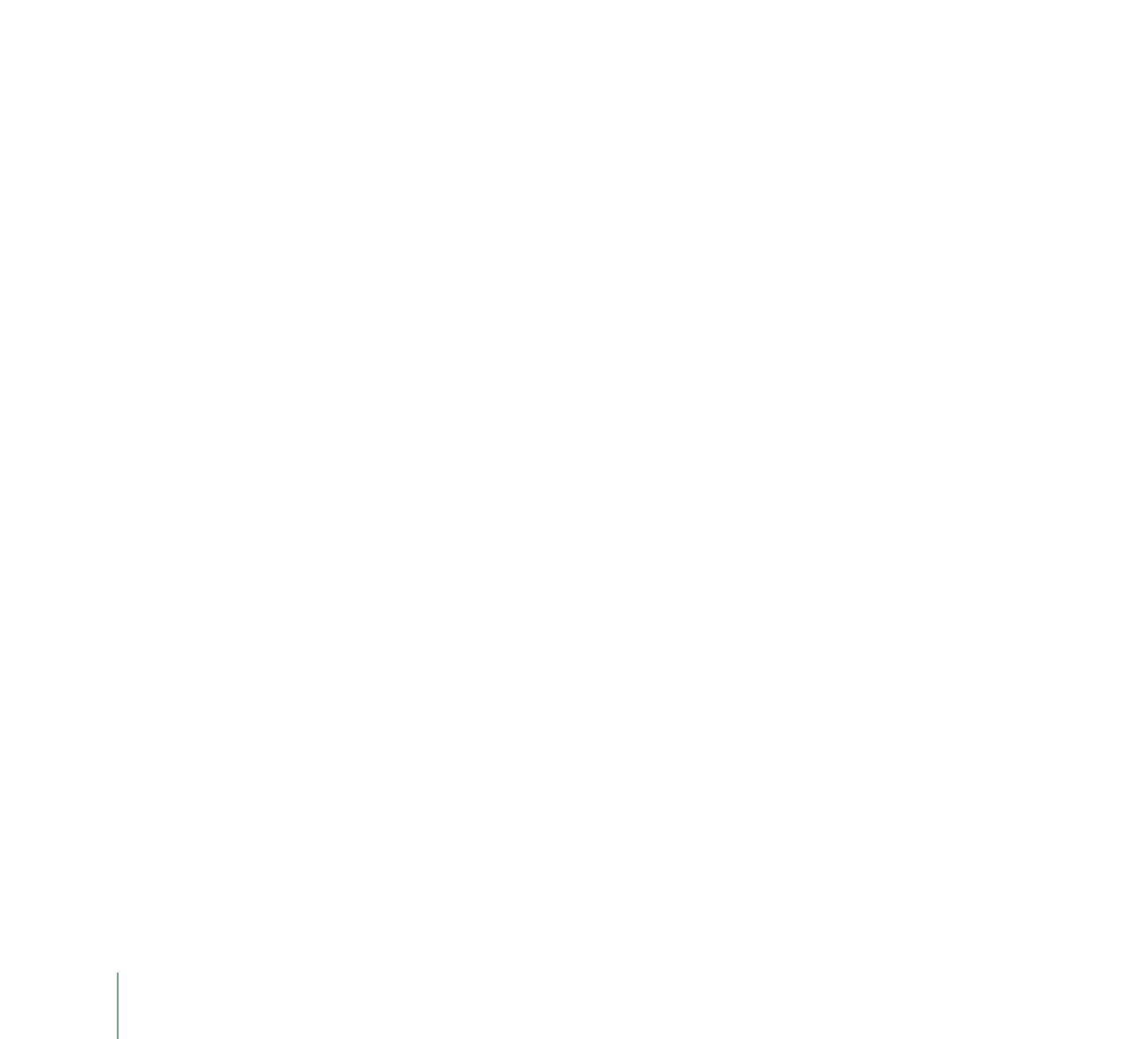
36
ウィーン、1791年。天才たちの居が並ぶ熱にうなされたようなこの街では、すでに過去の
ものとありつつあった古典主義がまださかんに行われていた。
オペラ座や劇場は宮廷のお歴々を迎え入れ、大公たちのサロンでは室内楽が演奏され、また、
羨望の的だったパリやマンハイムの管弦楽団の例にならうかのように、交響曲がやっと顔を出し
始めたところだった。しかし
18
世紀末のウィーンはそれだけにとどまらない。
1770
年から
75
年にか
けて吹き荒れた「疾風怒濤」の嵐が去ってからは、政治不安と、パリで起こった恐るべき革命の余
韻が広がっていたのである。やっと頭をもたげ始めた市民階級は、これまでと何ら変わることのな
い政体とは相容れないものとなっていた。
そんな中、ヒーロー神話が生まれかけていた。全てを敵にまわしてたった一人で戦う者が、君主
たちのあとを継いだのだ。そのお気に入りの武器の一つは「フォルテピアノ」といって、チェンバロ
に取って代わっていった。フォルテピアノとチェンバロは同じ哲学的道理には属さない楽器なの
だ。
ハイドンやモーツァルトの指が奏でる新しい鍵盤楽器が、聴く人を不意に呼び止める。グラーフ、
スタイン、ジルバーマン、さらにはブロードウッド、プレイエル、エラールなどの楽器製造者が自作
の楽器を貸したり贈ったりすることで、強い音響を誇るピアノは、どんどんと広く大きくなってゆく演
奏会場に場を占めるようになった。
協奏曲、ソナタ、変奏曲など、あらゆるジャンルの音楽は、もう貴族たちを楽しませるだけの音楽
ではなくなっていた。音楽合戦――
1781
年末に皇帝の前でモーツァルトとクレメンティが行った有
名な演奏合戦など――は、斬新な和声の探求の場となり、常により大胆な形で内面の発露が行
われるようになってゆくのである。
ウィーンでは、モーツァルトがバッハのフーガに出会ったところだった。
フーガという音楽に触れて、モーツァルトは「やっと何かを学んだ!」と叫んだかもしれない。しか
し同時に彼は、自由や新しい表現法も主張していったのだ。ドイツ語で「エンプフィントサムカイ
ト」を呼ばれる感性は、いまだにギャラント様式で飾られてはいるものの、芸術家の感性を丸出し
にするものだった。楽譜を追うに従って、伝統的な型が薄れていく。アルベルティ・バスから解放
されて、やっと音符が保たれメロディーが自由に歌えるようになった今、モーツァルトはより冒険味
に満ちた、流れるような話法を探求するのであった。
モーツァルト/ベートーヴェン/シューベルト