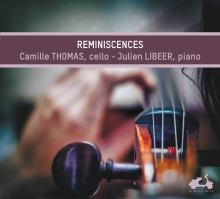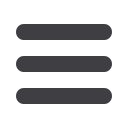
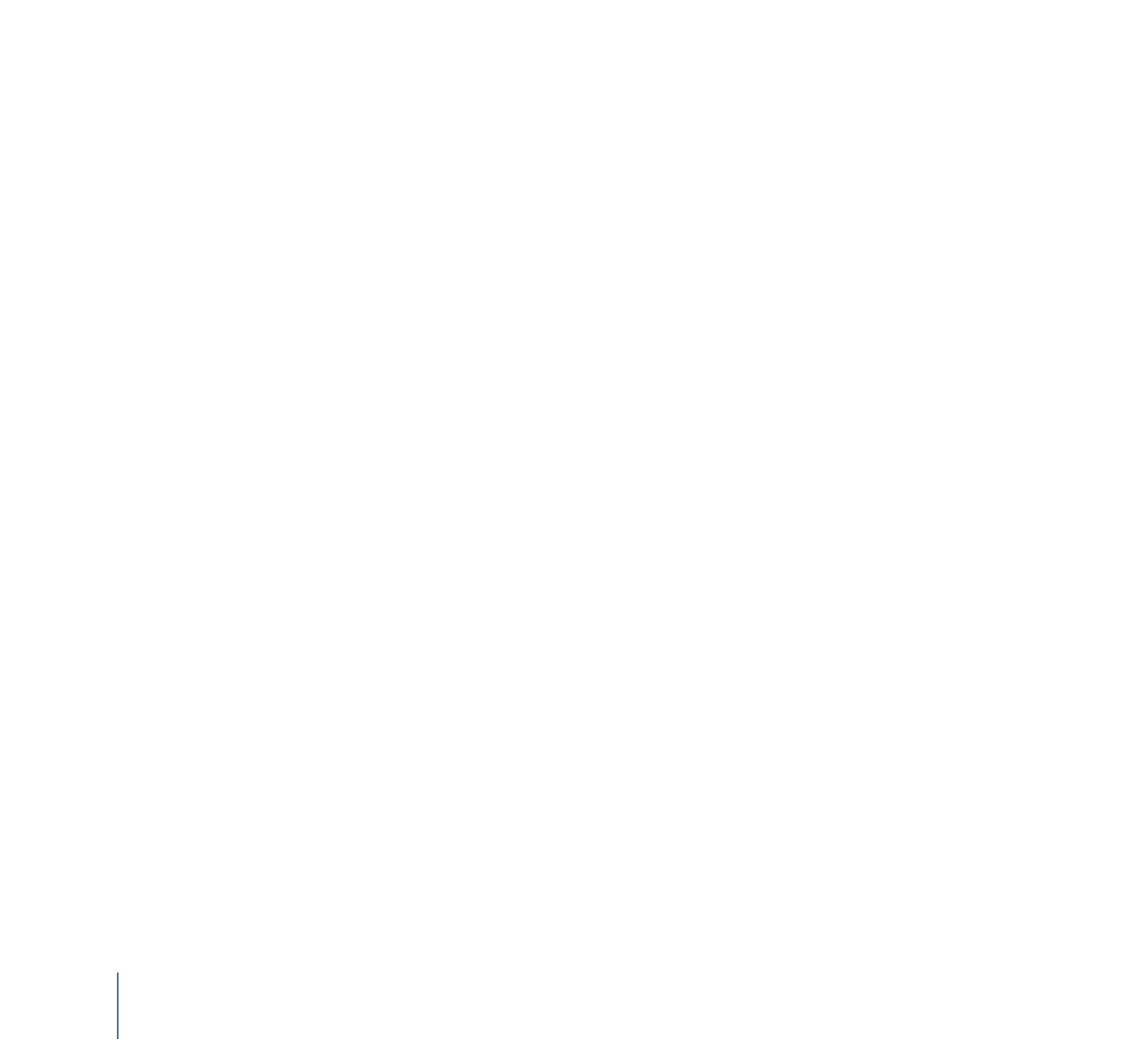
34
追憶 固有の世界
ピアニストにとって、このチェロ版の難しさはどこにあるのでしょうか?
J.L.:
ピアノ・パートは原曲と同じです。ただし、ヴァイオリンよりもチェロのほうがピアノと音
域が近いので、バランスを考慮する必要はあります。さらに、チェロよりもヴァイオリンで演奏
するほうが、音楽がスムーズかつ有機的に流れる曲であるため、ピアニストには柔軟性が
求められます。幸いにもこのソナタの書法は、これを容易にしてくれます――ワーグナーか
らの影響が色濃い書法に、深く掘り下げられたメッセージが込められているからです。半音
階を多用した遠回しの音楽表現が、ピアニストに柔軟性をもたらしてくれるのです。これは
もっと古典的な性格のソナタには見出せない特徴でしょう――例えば、フォーレの《ヴァイ
オリン・ソナタ》をチェロとピアノで演奏できるとは思いません。今回の《チェロ・ソナタ》の編
曲は、フランク本人ではなく、デルサール(注
1
)によるものです。ちなみにカミーユはこの編
曲版を用いながらも、チェロで演奏しやすいように手を加えられたアレンジのうち、原曲の
意図を歪めていると判断したものは採用しませんでした。
C.T.:
採用しなかったのは、いくつかのパッセージのオクターヴです。私は、オクターヴに
頼ってチェロで“楽に” 高音を出す方法を拒んだわけです。当然それによって、技術的に
も表現の面でも難しいパッセージに挑まねばなりませんでした。幸いにもジュリアンは、私
のこのような音響的・音楽的な理想の追求に、根気よく付き合ってくれました…
注
1
:ジュール・デルサール(
1844-1900
)は、フランスのチェロ奏者、教育者。パリ音楽院でオーギュスト・フランコム
(
1808
-
1884
)に師事し、
1884
年から師を継いで同院で教鞭を執った。